前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。
今回は、契約不適合責任が発生した際に買主が請求できる権利についてご説明します。
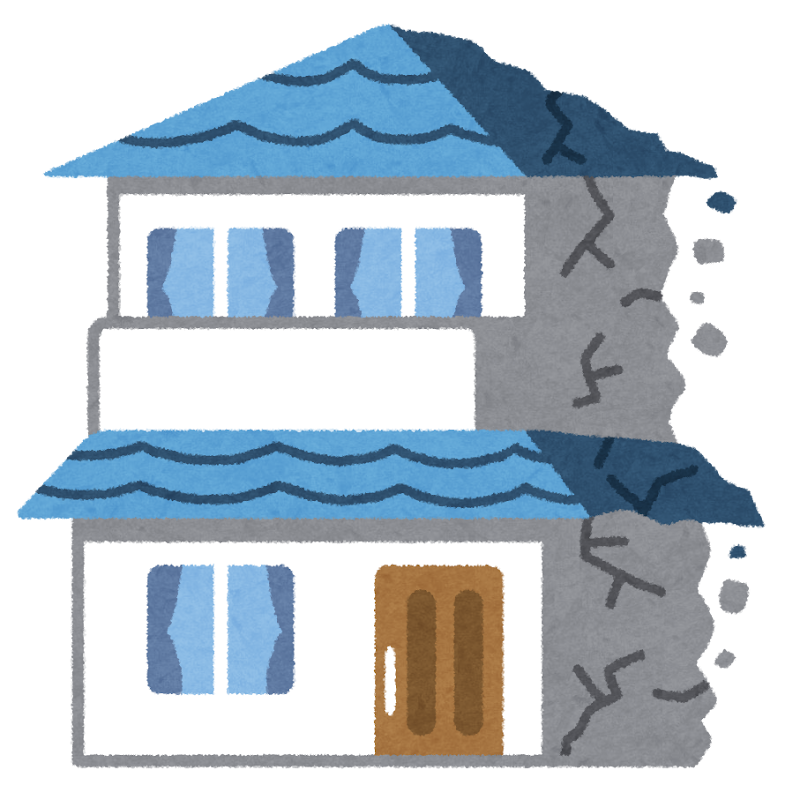
買主が購入した不動産に瑕疵があることを発見し、売主に対して請求できる権利は、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、契約解除権の4種類です。
まず、追完請求権とは、民法第562条第1項において「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」と定められています。
つまり買主は、引き渡された土地や建物に契約内容と不適合する部分(瑕疵)を売主に対して補修工事などの方法によって、契約内容に適合させるように請求することができます。
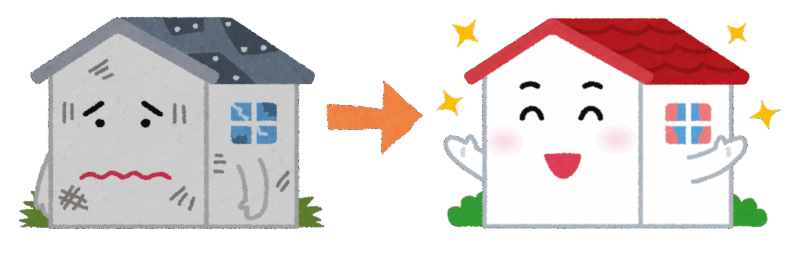
次に、代金減額請求権とは、民法第563条第1項において「前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる」とされています。
これは、買主が前述した追完請求権に基づき、売主へ履行の追完を請求したものの、売主が履行の追完を拒否した場合や履行の追完が不可能な場合に請求できる権利です。
引き渡された不動産が契約内容と不適合な部分の程度に応じて、売買代金の減額を請求することができます。
次回も引き続き、買主が請求できる権利についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産を是非よろしくお願い致します。
民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
マルタ不動産 髙木

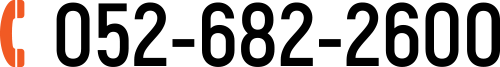
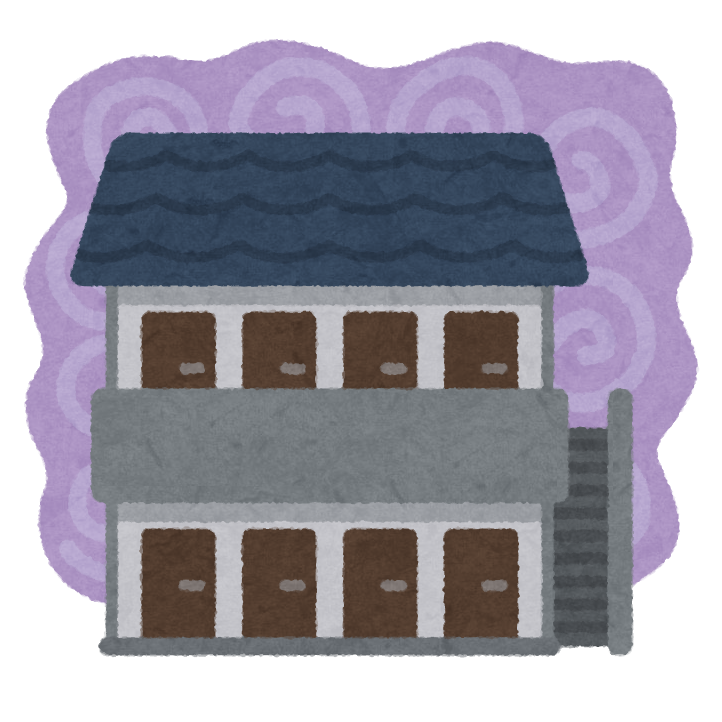

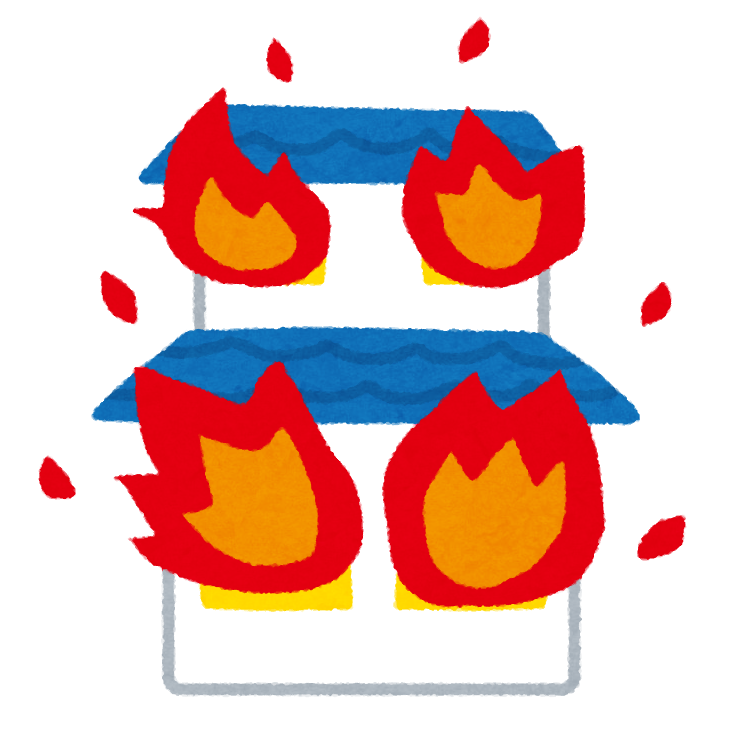
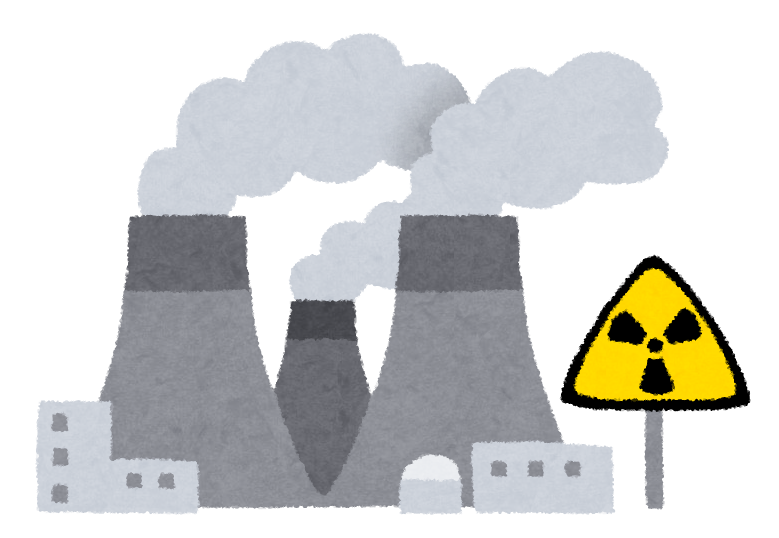
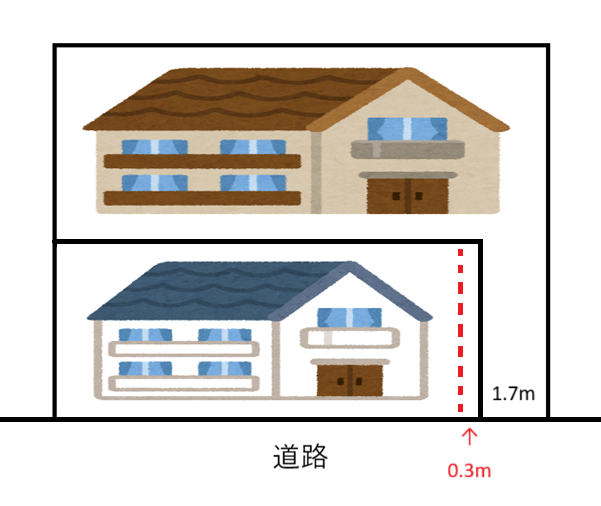


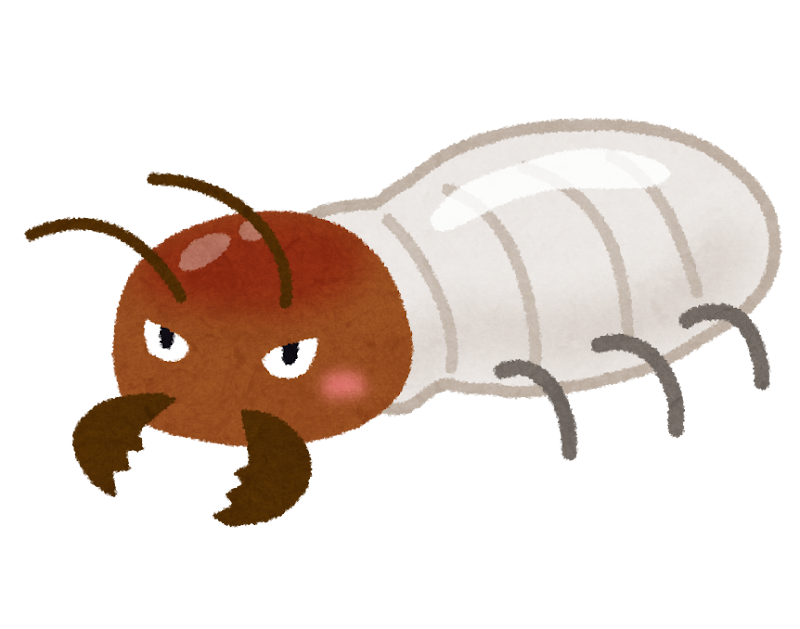

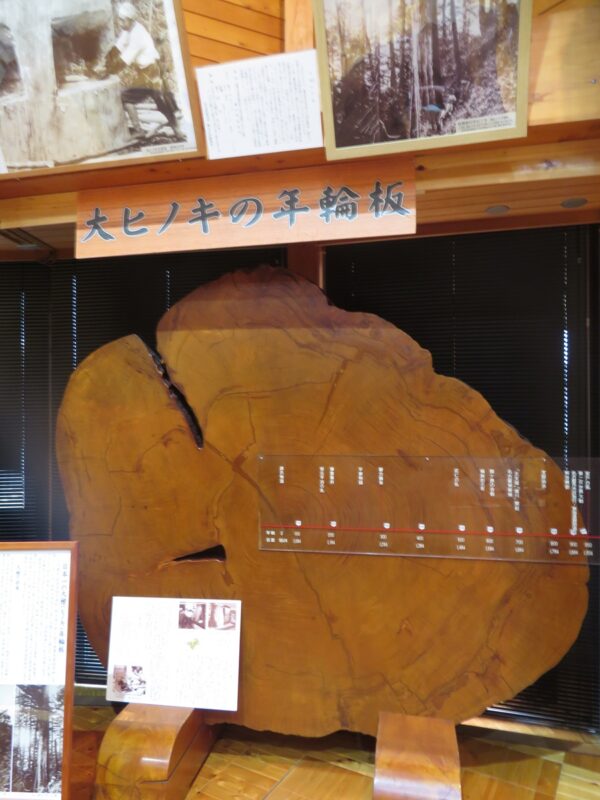
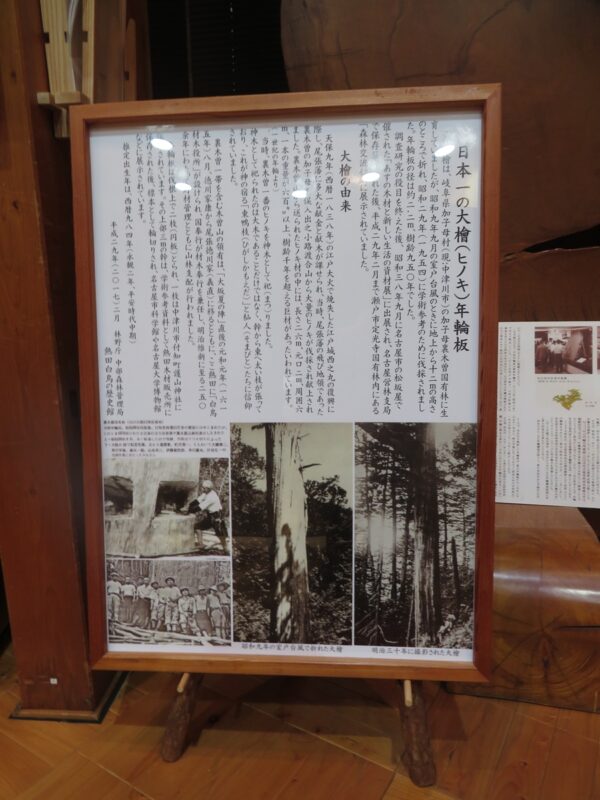
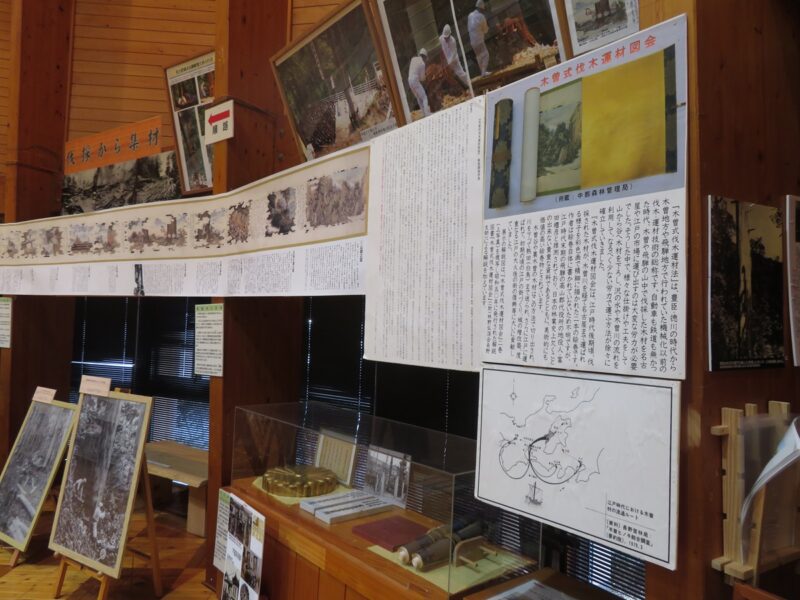






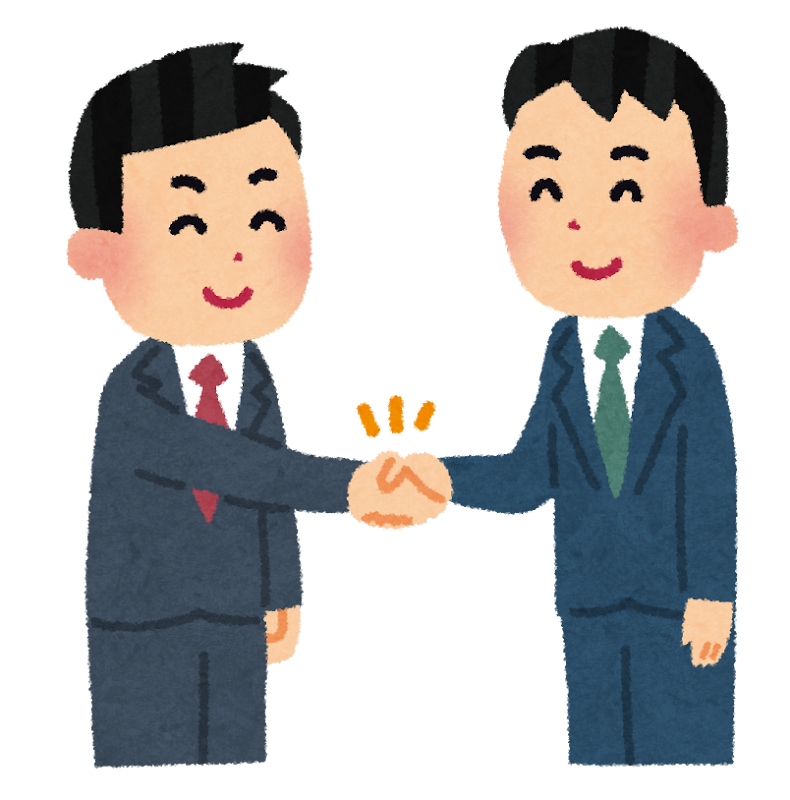




250802_165434-800x600.jpg)


