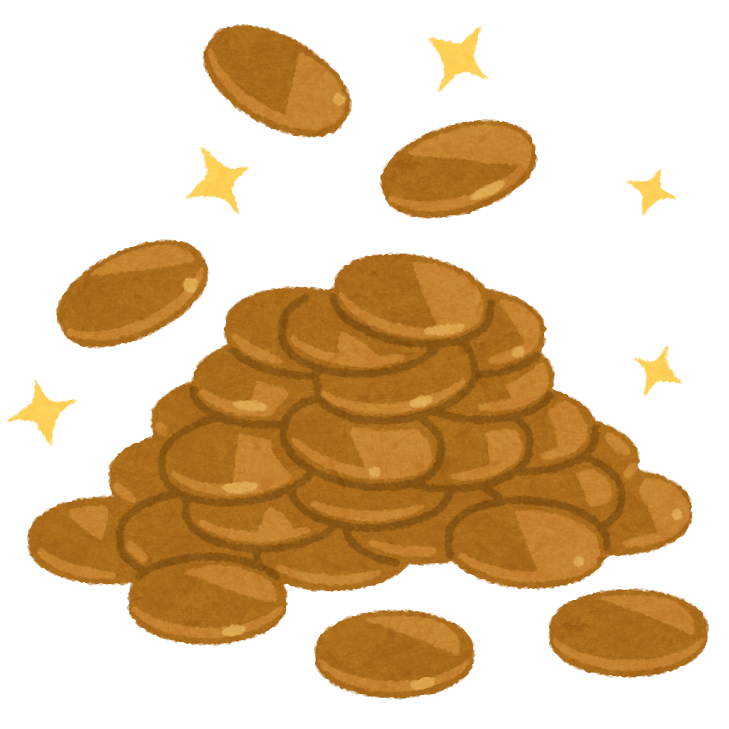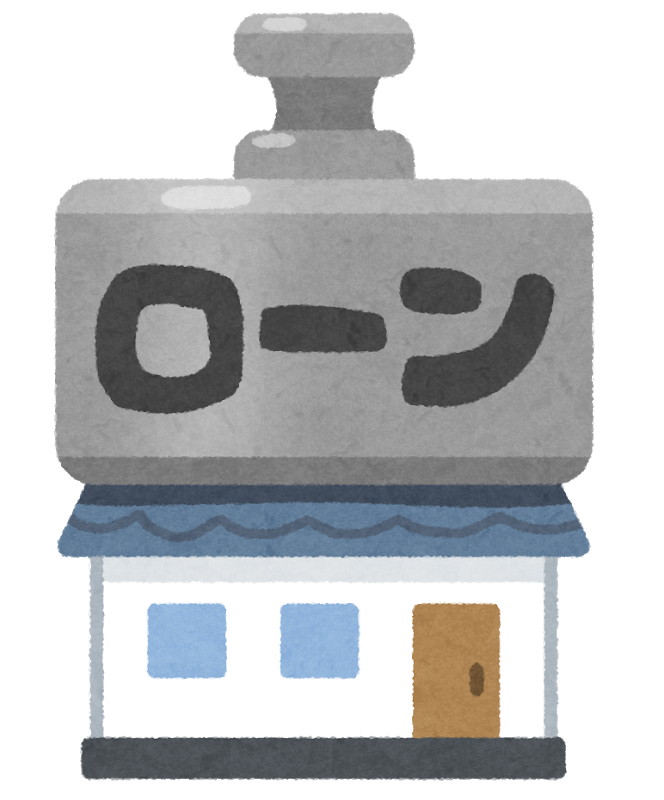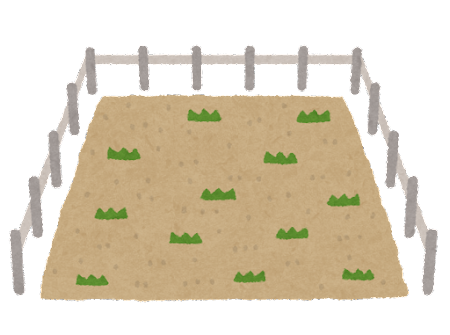市街化区域に不動産を所有していると4月から5月にかけて、固定資産税と都市計画税の通知が来ます。
毎年、なんとなく支払いをしている場合が多いと思いますが、今回は固定資産税と都市計画税(以下固定資産税等)についてちょっとした豆知識をお伝えしようと思います。
まず、固定資産税等の支払い義務者は1月1日に不動産を所有している人で、1年分の課税がされます。仮に1月2日不動産を売却したとしても、1月1日に所有していた人に固定資産税等を1年分全額支払う義務があります。逆に1月2日に所有した人は支払いをする義務は全くありません。
但し、通常の不動産取引では、当事者間で固定資産税等の精算の取り決めをしますので、不公平は生じません。しかし、それはあくまでも当事者間の取り決めですので、納付書を次の所有者の方に渡して、万が一支払いがされませんとそれは1月1日の所有者の方の滞納になってしまいます。納付書を他の人に渡すのでなく、精算金を受け取りご自身で納税するのが良いです。
また、当事者間の固定資産税の精算は税金として払うものでなく、土地、建物の取引代金の一部とみなされます。ですから、事業者から購入する建物にかかる固定資産税を当事者間で精算すると、その精算金に対して消費税がかかります。税金にさらに税金がかかっているような気になりますが、そういうルールになっています。

1月1日時点で所有者が亡くなっている場合はどうなるのでしょう?だれが納税義務者になるのでしょうか? 答えは相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。つまり自治体は誰にでも全額の請求をできるということです。請求された人にとっては、他の人の分まで支払うことになり不公平感がありますが、そういう制度になっているそうです。相続が円満にすすめば良いですが、その後のシコリになってしまいそうですね。
マルタ 岩城
賃貸マンションや賃貸アパートなどに住んでいる方は、次の場所へ引っ越す際に「退去費用」が発生します。その退去費用とは、原状回復のために必要になる設備の修繕費用や、ハウスクリーニングの費用など、次の住人が住める状態にするために必要なお金のことを指します。しかし、住居は通常の使い方で使用していても時間ともに劣化していくものです。その時間と共に劣化したものまで、借主側だけが負担し入居当時の状況に戻すということはかなり借主側にとっては非常に負担が重くなってします。その為、一部は貸主にも負担してもらうということが、国土交通省で定められています。(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)
そこで今回はどのようなものが借主の負担になるのか、またどのようなものが貸主負担なのかをお話していきたいと思います。
退去時に支払わなくてもすむ費用の具体例について
・家具家電を設置したことによる床のへこみ
・電化製品の電気焼けによる壁の黒ずみ
・ポスターやカレンダーによって壁にできた跡
・画鋲やピンの穴(小さいもの)
・浴槽の補修費(経年劣化によるもの)
・台風や震災による損傷
・エアコンの内部洗浄(手の届かない範囲) etc.
のようなものがあげられます。つまり「通常消耗(だれが住んででもどんなに気を付けて暮らしていたとしても、人が住んでいれば少なからず傷んでしまうもののこと)」と「経年劣化(時間の経過によって品質が下がってしまうことで、直射日光で壁紙が変色したり、湿気で窓枠のゴムが傷んでしまうこと)」は借主が支払わなくてもよいものということです。
次に退去時に支払う必要のある費用の具体例について
・食べ物や飲み物をこぼしてできたシミ
・ものを落とした、家具を引き摺ったなどしてできたフローリングの傷
・ペットが付けた汚れ
・子どもの落書き
・タバコの臭いや壁の黄ばみ
・鍵をなくしたときの交換費用 etc.
のようなものがあげられます。ただしこれらも原状回復のためにかかる費用全てを負担するのではなく、貸主の負担となる費用を差し引いた分を負担する形になります。経年劣化や通常損耗による損害分を引いた分を、入居者側が負担する形になります。
今回はのガイドラインはあくまで、契約書に書いていなかったときに双方間でもめない為に役に立つものであって契約書のように法的強制力があるものではないので、契約書を上回って認められるものではないということは理解しておきましょう。
マルタ不動産 辻石
今回は、前回に引き続いて、防火地域と準防火地域の建物の規制緩和についてご紹介したいと思います。
防火地域と準防火地域の建物の規制緩和は、過去にブログでご紹介した建物の規制緩和とは、少し異なります。
まず、防火地域の建物の規制緩和ですが、防火地域に建てる耐火建築物は、建ぺい率の緩和が適用されます。
全ての建物は、民法第234条において、「建物を建造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とさ定められています。
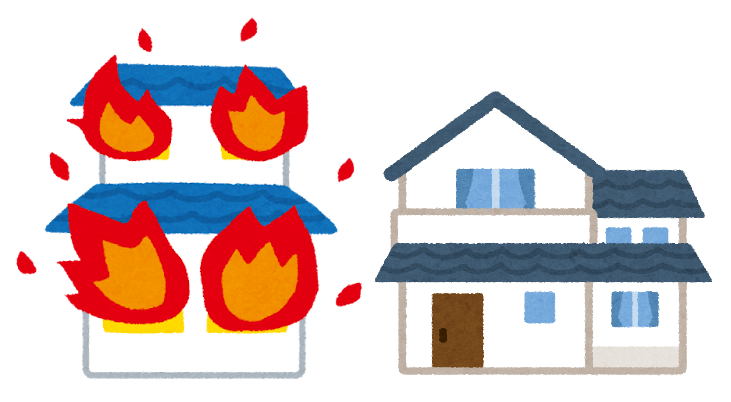
しかし、耐防火地域内の耐火建築物は建築基準法第63条において、「外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定められているため、通常よりも敷地面積を活用して建物を建てることが可能となります。
これに加えて、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建ぺい率が80%に制限されている地域では、建ぺい率の制限はなくなり、それ以外の地域では、法定の建ぺい率より10%緩和されます。
次に、準防火地域の建物の規制緩和ですが、2019(令和元)年6月に施行された建築基準法の一部を改正する法律において、準防火地域に建てる耐火建築物、準耐火建築物お及びこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物も建ぺい率が10%緩和される対象に定められました。
この改正の背景には、新潟県の糸魚川大規模火災などの大規模火災によって甚大な被害があります。住宅が密集する準防火地域の建ぺい率を緩和することで、耐火建築物への建て替えを促進する狙いがあります。
もし、建て替えや土地の購入を検討される場合、その地域が防火地域や準防火地域に該当するかどうか調べてみるのも良いかもしれません。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
建築基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053
マルタ不動産 髙木
新年あけましておめでとうございます。
2025年は巳年にあたり、新たな一年がはじまりました。蛇は脱皮を通じて成長するため、巳年は自己変革や新しい始まりをするのに良いと言われています。
昨年は、不動産市況においても多くの変化が見られましたが、本年も引き続き、皆様の住まい探しや不動産売却を全力でサポートさせていただきます。
中古マンションについては、昨年から名古屋、三河地方では動きが鈍くなってきておりますが、逆に購入希望の方には多くの物件の選択肢があり、良い状況と思います。
利上げやインフレで、出費が増えていく状況が続いていくと言われております。これからもこちらのブログで皆様のお役に立てる情報をお伝えするように努めてまいります。
皆様のご多幸とご健康を祈念し、良い不動産取引ができるように、スタッフ一同、尽力してまいります。
どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。
マルタ不動産 岩城
募集中だった弊社の所有する熱田区四番一丁目16-16 ハットリビルの一階の店舗にこの度中華料理店が入ることになりました。
先月、11月20日からオープンしており、店名は「祥和」です。
祥和はもともと昭和区の阿由知通にあったお店で、昨年の12月30日に建物の立ち退きに伴って惜しまれつつも閉店したお店です。
お店は中国出身のご夫婦で営まれており、本格派中華料理を食べることができます。

前テナントも中華料理店だったので居抜き(設備や内装など前テナントの時に使用していたもので使えるものは使いつつ新しく営業すること)で利用されることが多いのですが、今回は店舗内をすべて解体し店内の内装・設備をすべて一新してのオープンになっている為、店内もすごくきれいです。
靴を脱いでの半個室も設けてあるので、これから迎える忘年会や新年会などもバッチリだと思います。
また、店舗は国道一号沿いで地下鉄名港線の六番町駅降りてすぐの場所にあり立地条件もバッチリなところにあります。
お昼の時間帯はランチもやっており、麵+飯や定食、日替わりメニューなどバリエーションも多くお値打ちに食べることができます。
わたくしも近くにすんでいるので、オープンしてすぐに早速一度食べに行きましたが、麻婆豆腐が程よい辛さでとてもおいしくお勧めです。皆さんも、是非一度立ち寄ってみてください。




マルタ不動産 辻石
住宅をいつ買うのが良いのか?
これには色々な考え方があると思います。
住宅ローンの金利の動向も気になるし、
安いときに買いたいし、高くは買いたくない。
これは自然な感情だと思います。
私の一つの考えは、「ライフプランを考えて購入する。」です。
子供がもうすぐ巣立つタイミングに4LDKのファミリータイプの広いマンションを購入しても、すぐに持て余すようになってしまします。
たとえ、どれほど安く購入できたとしても、良い購入とは言い難いです。
不動産で儲けてやろうと思うのであれば、良い取引かもしれませんが、不動産のプロでも利益を出すことは難しいです。
子供が小さいときに購入していれば、購入金額が多少高かったとしてもファミリータイプのマンションは良い選択になると思います。
仮に10年早くに購入できたとすると、経済面でも10年分の家賃がなくなりますし、なによりも子供の成長が10年分良い環境で過ごせます。
子供が小さいときというのは、まさに不動産を買うのには良いタイミングと思います。
そうでない場合も、あまり先のことは分かりませんが、10年くらい先であればイメージがつきやすいです。自分のライフプランにあわせて、考えると良いと思います。
マルタ不動産 岩城
この季節天気が良く洗濯物を外に干した状態で、外出して急なゲリラ豪雨でせっかくの洗濯物が台無しに・・・みたいな経験が一度はあるのではないでしょうか。
そんな時、浴室乾燥機があると天候の悪い日や冬の寒い時期でも洗濯物を安心して乾かすことができるのは大変便利です。
なので、弊社のマンションリノベーションではすべて電気式の浴室暖房乾燥機を設置しています。
今回は、浴室乾燥機の種類についてお話していこうと思います。
浴室乾燥機には、大きくわけるとガス式と電気式2つの種類があります。
まず、ガス式について
ガス式の浴室乾燥機は、浴室の外側にガス温水器(給湯器など)設置して、その熱源内にてお湯を循環させることで熱を作り出し浴室を乾燥させるというタイプになります。
このガス式の最大のメリットはのち程説明する電気式に比べてパワーがかなり強力で乾燥時間が短くすむということでしょう。
続いて、電気式について
電気式の浴室乾燥機は、さらに「電気ヒーター式」「ヒートポンプ式」という二つに分かれます。浴室乾燥機本体の内部で自ら熱を作り出し乾燥させるのが電気ヒーター式です。外部空間から空気を利用して熱を発生させて浴室の乾燥・暖房に利用するのがヒートポンプ式です。この電気式浴室乾燥機のメリットは、設置スペースがコンパクトで初期費用がガス式にくらべてあまりかからないことです。
設置スペースが限られているマンションでは、こちらの電気式が設置されることが多いです。このことから弊社のマンションリノベーションでもこちらの電気式を設置しています。
どちらも既存のユニットバスに後から取り付ける方法があるので、今、ご自宅に浴室暖房乾燥機がない方も一度ご検討してみてください。
マルタ不動産㈱ 辻石
日米の金利差、ゼロ金利政策の解除、金利上昇とこんな言葉を耳にするようになり、ずいぶんになります。
歴史的円安の背景は日米の金利差にあると言われており、金利という言葉をよく耳にします。
アメリカでは強いインフレで金利がかなり上昇しています。
しかし、日本は金利が低く、アメリカと日本の金利差が円安を引き起こしているそうです。
やがて日本でもインフレに伴い、金利が上昇すると言われています。
今年の3月に、日銀がマイナス金利政策の撤廃を決め、金利のある日本になってきました。
普通預金の金利は、なんと20倍になり、メガバンクでは0.02%となっています。
では、住宅ローンの金利はどうでしょうか?
実は、ほとんどの人の選択する変動金利は、変わっていません。
最も低い水準のままです。
一方、フラット35などの固定金利は上昇しています。
とは言え、固定金利も低水準にあります。
では、どちらの金利を選ぶのがよいのでしょか?
僕の考えは、住宅ローンの支払いに余裕のあり、リスクを取れる方は、変動金利が良いと思います。
住宅ローンの支払いで頑張っている方は、今後のライフプランが組みやすい固定金利が良いと思います。
大切なことは、住宅ローンのことだけでなく、教育費などの将来のライフプランに合わせた選択をすることです。
もっと、大切なことは、自分のライフプランにあった不動産を選択することです。
ここが、一番の肝になります。
マルタ不動産 岩城

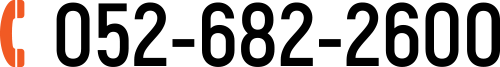
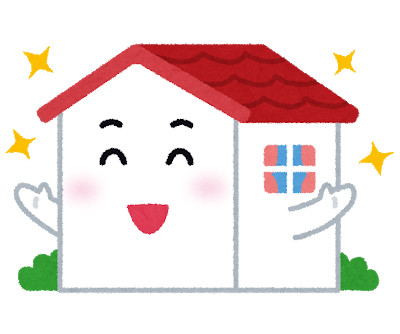







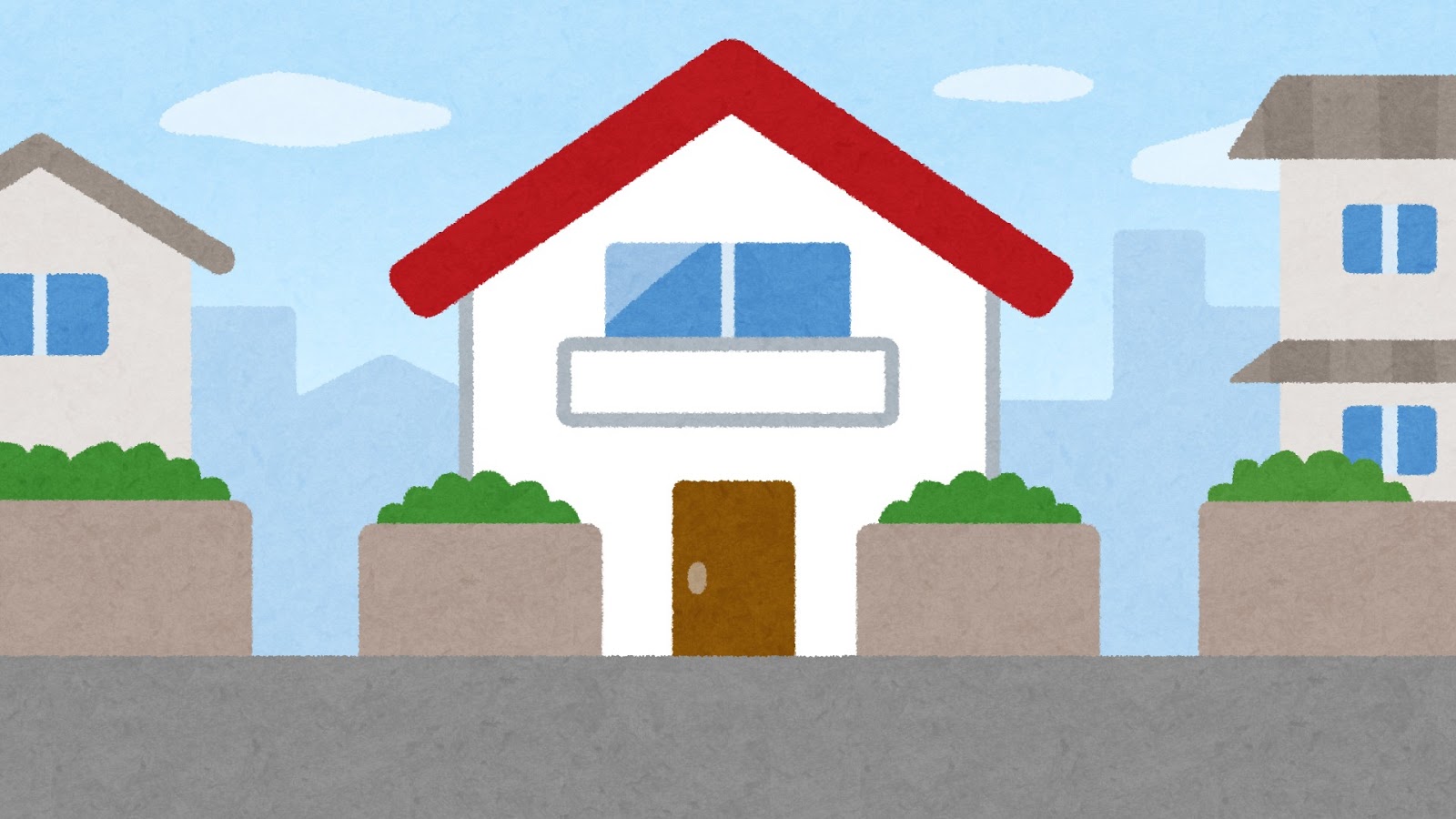

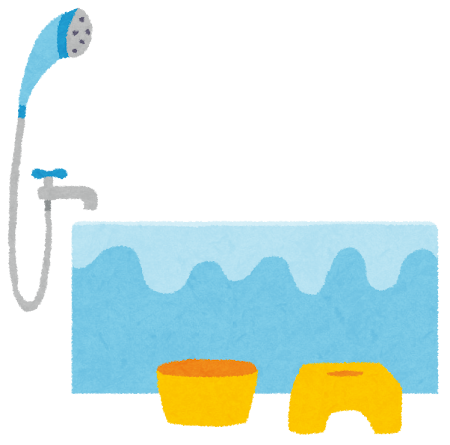

240802_105431-1-800x600.jpg)
240802_105431-2-800x600.jpg)