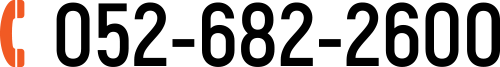農地法によって農地が守られていることは、前回ご説明しましたが、具体的にどのような規制で農地を保護しているかご紹介したいと思います。
今回ご紹介する規制は、農地又は採草放牧地の権利移動の制限です。
この制限は、農地法第3条において「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない 。」と定められています。
この条文の通り、農地を購入、または貸借する時には、原則的に農業委員会の許可が必要です。
しかし、第3条第2項では、これからご紹介する7つの条件に当てはまる場合は、権利移動の許可をすることができないと定められています。
1つ目の条件は、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員が、農業に必要な機械の所有状況や農作業に従事する人の人数及び技術からみて、農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用すると認められない場合です。この農地及び採草放牧地のすべては、元々所有している農地も含まれます。
2つ目は、農地所有適格法人以外の法人が所有権などの権利を取得しようとする場合です。一般の法人は、原則的に農地に関する権利を取得することはできません。
3つ目は、信託の引き受けにより所有権などの権利が取得される場合です。信託会社や信託銀行などは、信託引き受けをして、農地の権利を取得することはできません。
4つ目は、農地所有適格法人を除く、所有権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員が、農地や採草放牧地の取得後に農作業に常時従事すると認められない場合です。常時従事とは、農作業の従事の年間日数が150日以上あることを言います。しかし、150日未満の場合は農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば常時従事と認められます。
5つ目は、所有権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農業をするための農地の面積の合計が、農地や採草放牧地の取得後、北海道の場合では2ヘクタール、そのほかの都府県では50アールに達しない場合です。但し、農業委員会がこれらの面積の範囲内で別段の面積を定めたときはその面積となります。
6つ目は、農地や採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合です。農地を借りている人がさらに他の人へ貸す事を防止する規制です。
7つ目は、所有権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農地や採草放牧地を取得後に行う農業の内容、位置、規模からみて、農地の集団化、農地の効率化など農地や採草放牧地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合です。
農業委員会から権利移動の許可を得ずに他人に農地を売却した場合、所有権などの権利は買主に移転しません。違反者には、「3年以下の懲役又は300万以下の罰金」に処される場合がありますので、注意が必要です。
次回も引き続き、農地法の規制についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
農地法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
マルタ不動産 髙木