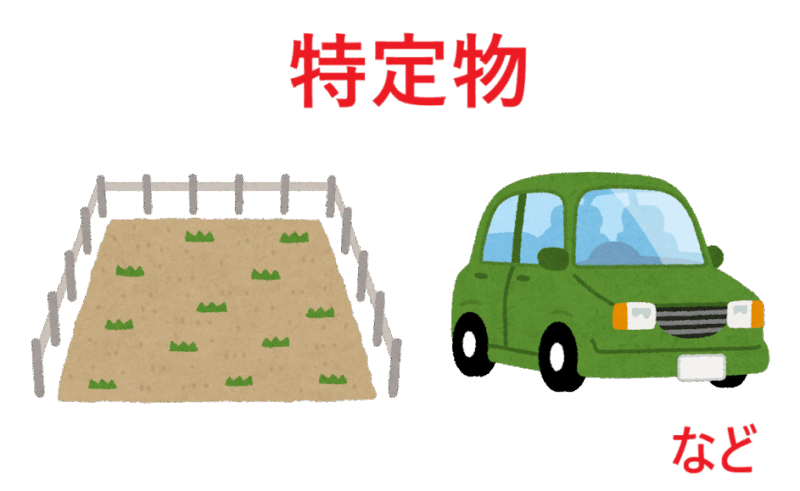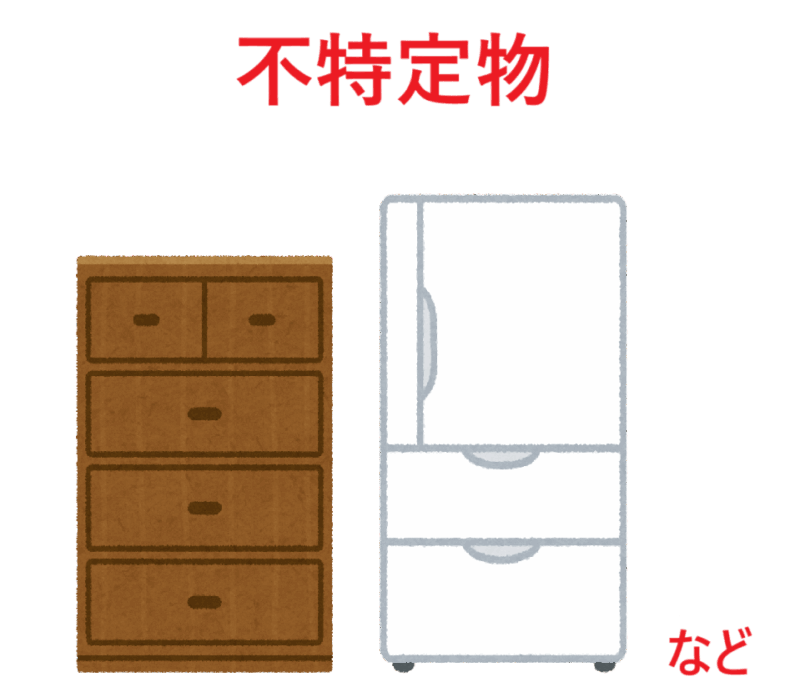Skip to content
以前のブログで契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてご紹介してきました。
今回は、そもそも2020年4月の民法改正で従来の瑕疵担保責任と現在の契約不適合責任にどのような違いがあるのかご説明したいと思います。
まず、1つ目の違いは、責任の対象の範囲です。
従来の瑕疵担保責任では、特定物にしか補償が適用されませんでした。
この特定物とは、取引の当事者が個性に着目した取引の目的物のことをさします。具体例を挙げると、不動産や中古車(状態や走行年数、走行距離が個々で異なり、まったく同じ状態のものが滅多にないため)などが該当します。
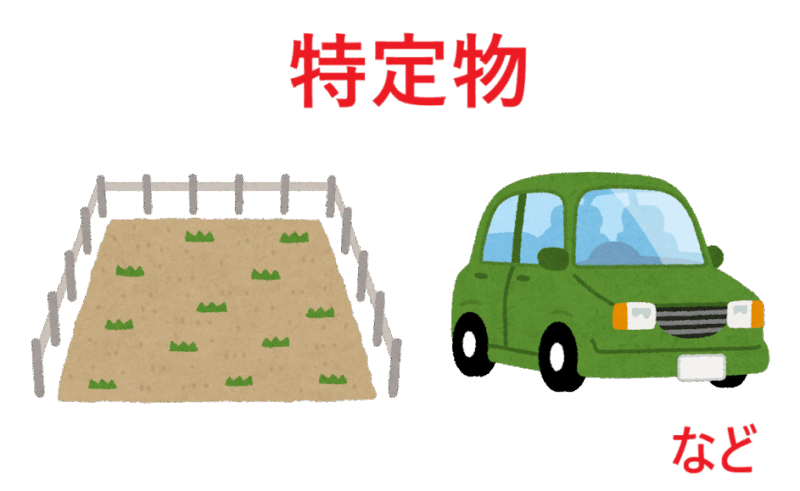
例えば、家具付きの物件を購入した場合、備え付けの家具は保証期間が1年以内と契約書に明記されていた場合、家具が一般的に流通している代替が可能なものの場合、不特定物に該当すると考えられ、保証期間が過ぎてしまうと買主に落ち度が無くても売主へ責任を追及することが出来ませんでした。
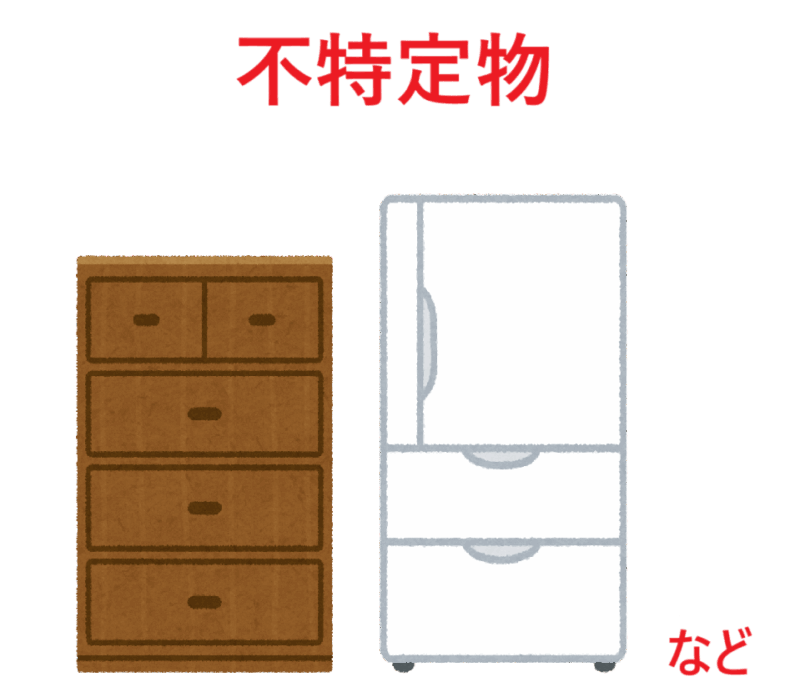
現在の契約不適合責任では、特定物か不特定かに関係なく、売買の対象物が契約目的と一致していなければ適用されます。
2つ目の違いは、買主が売主へ請求できる権利の数です。
瑕疵担保責任では、買主は売主に対して、損害賠償請求権と契約解除権しか行使できませんでした。しかも、契約解除権は、契約目的を達成できない場合にのみ限定されていました。
契約不適合責任では、以前のブログでもご紹介しましたが、従来からあった2つに加えて追完請求権、代金減額請求権も行使できるようになりました。
次回も引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産をよろしくお願い致します。
民法|e-Gov法令検索
マルタ不動産 髙木