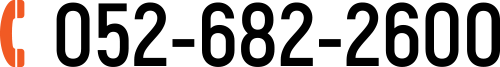皆様は、農地転用という言葉を見聞きしたことはありますか。
農地転用とは、いわゆる畑や田んぼなどの農地として使用していた土地を農地以外の目的で使用することです。しかし、この農地転用は、農地法によって規制を受けており、農地に家を建てたいと宅地に転用することが難しい場合があります。
相続などで農地を所有した時に、農業の経験がない場合は農地を自分が使える形に変更したいと考える方もいると思いますので、農地転用についてご紹介したいと思います。
まずは、そもそもの農地法の規制を受ける土地は、農地と採草放牧地の2種類あります。
同法第2条において、「「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。」と定められています。
そして、この定義に基づいて、農業委員会が農地かどうか判断します。この判断の際には、客観的な視点に基づく「現況主義」が採用されます。
「現況主義」では、登記事項証明書上では、農地ではない土地でも、農業に利用されていれば、農地にみなされます。そのため、逆に農地として登記されていたとしても、農業に利用されている形跡がないなど現況によっては、農地とみなされない事もあります。
しかし、休耕地や不耕作地だった場合は、農地として判断される場合もあるため、注意が必要です。
また、採草放牧地は、農地法上の土地区分であり、登記事項証明書上には、「採草放牧地」という地目はなく、「原野」や「牧場」という地目で取り扱われるため、こちらも注意が必要です。
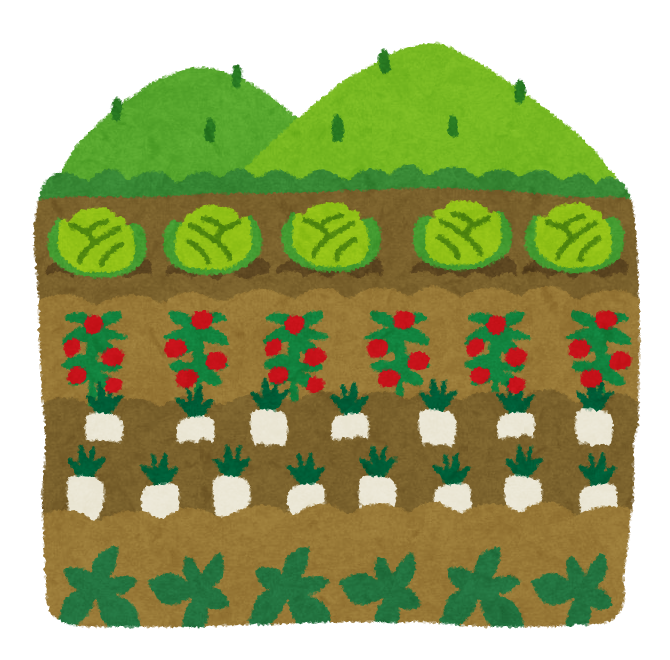
次回は、農地法の規制内容についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
農地法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
マルタ不動産 髙木